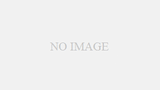現在デモシーンで活躍中の方にお話を伺う、「デモシーナーにインタビュー」 8回目(!)となる今回は、Farbrausch(ファーブラウシュ)のkbさんにお願いしました!
「Farbrauschのkbさん」といえば、もうそれ以上の説明はいらないような気もするんですが、とりあえず簡単にご紹介すると、、
Farbrausch: デモシーンで最も人気のあるグループの1つ。技術面と芸術面の両方でハイレベルの作品を生み出すことで知られていて、デモシーン最大のポータルサイト「Pouet」にあるオールタイム・トップランキングでは、1位の「debris」をはじめ、Farbrauschの作品がいくつもランクインしています。上位を目指すデモシーナーにとっては、Farbrauschは憧れであり、最大の敵でもあるようです。
kbさん: Farbrauschのメンバーであり、90年代初めから活動を続けるデモシーナー。コーダー、ミュージシャン、パーティーオーガナイザーと様々な分野で活動していますが、恐ろしいことにすべての分野で見事な活躍をされています(笑) デモシーンの“アイコン的な存在の1人”と言えるのではないでしょうか。
インタビューでは、Farbrauschにまつわる謎、デモシーンの権力争い(ダークな響き、、)、kbさんの制作環境、おすすめのお茶までお聞きしました!
それでは、Farbrauschのkbさんです!どうぞお楽しみください。
——————————————————————–
まずは簡単に自己紹介をお願いできますか?
こんにちは、Tammo(タモ)です。デモシーンでは「kb」という名前で活動しています。デモシーンのキャリアをスタートさせたのは1993年で、当時はThe Obsessed ManiacsというグループでC64(Commodore64)を使って作品を作っていました。その後はReflexやSmash Designsといったグループにいて、今はFarbrauschのメンバーです。主にコードを担当していますが、サントラを手がけた作品もいくつかあります。グループ以外のところでは、1997年からイースターの時期にドイツで開催されるデモパーティー「Revision」のオーガナイザーをやっていて、現在はBeam Team(会場のスクリーンで上映するコンテンツを管理するチーム)の責任者でもあります。
かなり小さな頃からコーディングに興味があったそうですが、コンピュータに初めて触れたのはいつだったのでしょう?
ボタンがついてるものが昔から好きだったんですよね。2才の時、両親が電気のスイッチの使い方を教えてくれて、その瞬間に僕の運命は決まったんですよ(笑) それで、6歳の時、お店でテレビとつながったタイプライターみたいな機械と出会うんです。これがコモドールコンピュータだったわけですが、シフトキーを叩いても何も起きなかったので、すごくガッカリしたのを覚えています…。だからこそ余計にこれが何なのか知りたいと思ったんでしょうね。そしたら父親がC64のマニュアルのコピーをくれて、“この機械をプログラムすればいろいろなことができる”と分かったものだからさあ大変。人生で初めて恋に落ちたんです。
6歳ですか!ちなみに、そのマニュアルのコピーってまだ持ってたりします?
いやー、もうないですね(笑) 僕の記憶が正しければ、本物のマニュアルがついたC64が手に入った時点で捨てたと思います(笑) もうそのマニュアルすらないです。今まで使ってきたコンピュータは、古いシステムが必要になる場合に備えて全部とってありますけどね。
わりと早い時期に自分の好きなものが分かっていたんですね(笑) どんなお子さんだったのでしょう?
基本的にいつも何かしていましたね。レゴで変な仕掛けを作ったり、祖父母からもらった古い電子機器を分解したり、実験的なことに使ってみたり…(あまり上手くいったとは言えませんけどね。ただ、コンデンサーが音を変えるっていうのはわりと早い時期に学習しました) あとはC64をいじったり、こういう遊びを全部組み合わせてみたり、、そういう子どもでした。「典型的なオタクの子」と言ってもいいです。
なるほど(笑) では、デモやデモシーンとはいつ、どのようなきっかけで出会ったのでしょう?
最初の出会いはC64のゲームに入っていた初期のクラックトロだったと思います。その後にイントロだけがぎっしりつまったディスクを手に入れて、そこで興味を持つようになりました。普通はゲームの後に入ってるものなんですけど、それはイントロだけが入ってたんですよね。当時、趣味で音楽とか映像をやってる人たちが、変な名前を使って(イントロの中で)交流していたんですよ。あとは、「あれ?何であんな場所に絵が出てるんだ?」っていう感じのものが多かったですね。
それで、90年代の初めにはドイツで毎月のようにC64のディスクマガジンが発売されていて、その1つが“ちょっとしたデモをマガジンに送って優勝すれば50マルク(今だと25ユーロくらい)がもらえる”っていう小さなデモコンポをやってたんです。僕も僕の友達もデモには興味があったんですが、シーンには興味がなくて。でも、そのコンポをきっかけにThe Obsessed Maniacsのメンバーと知り合って参加することになったんです。
初めてデモを作った時のことを覚えていますか?仕上げるのに時間はかかりましたか?
初めて作った“ビッグデモ”(「Who Cares (TM)」)は、完成させるのに1年近くかかりました。パートが順番に出てきて途中にロード画面が表示されるような王道のメガデモだったので、それほどプロセスは踏んでいないんですけどね。できたものを組み合わせて作品にしたっていう感じです。それで、出来上がったものが入ったディスクを他の人に配るかたちでリリースしました。デモパーティーに出る、出ないっていう話は、それから1年後のことですね(笑)
それ以降、たくさん作品をリリースされていいますよね! Kbさんは90年代にThe Obsessed Maniacsの他にもいろいろなグループに所属されていたようですが、2000年になって新しくFarbrauschを結成しています。なぜそのタイミングで新しいグループを始めようと思ったのですか?
Farbrauschは、不満がつのっていたところから生まれたグループなんです。当時、YodaとRonnyと僕は、前のグループで起きた権力争いにウンザリしていたんですよね。「リーダー」って名乗りだしたりとか、自分が関わってもいない作品にまで口を出してきたりとか、グループ内でしょうもないケンカをしてたんです。そんなことが続くと、“デモを作る”っていうグループに参加したそもそもの理由から遠ざかるばかりでしたね。
それと、その頃、その揉めてたグループとは別に自分たちで「Elitegroup(エリートグループ)」っていう単発的なグループを組んで新鮮な体験をしていたんです。これは2014年になってもまだオールドスクールのグループがこだわってるデモシーン用語を皮肉って付けたグループ名なんですけどね。それで、これがすごく楽しかっただけじゃなくて、以前より自分たちがクリエイティブになれた気がしていたんです。
“Kasparov” by Elitegroup (1999)
だからFarbrauschは、“後ろめたさを感じることなく、デモを作ろう”っていうシンプルな前提のもとに3人で結成しました。基本的にFRのメンバーは自分がやりたいことを何でもやっていいことになっていて、グループから出すものに口を出すリーダーとか委員会みたいなのは存在しないんです。元ElitegroupのChaosやFiver2とか、これでずいぶんいろんな人が集まってくれましたね。
64kのジャンルを新しい形で復活させたことで名前が知られるようになってからも、結成時に決めた基本的な原則は変わっていないんです。正直なことを言えば、FRの名前でリリースしてほしくない作品も過去にはありましたけど、それは僕が決めることではないので。自分では、8時間続く4kイントロを「fr-」の番号をつけて出せる日が来ればいいなと思っています(笑)
ちょっと気になったのですが、、、そういう“グループ内での権力争い”って、デモシーンではよくあることなんですか?
いや、今はないですね。こういう争いは、まだインターネットが普及していなくて、ヨーロッパの国やそれ以外の場所にもディスクを郵送してた時代によく起きていました。そういう状態だと、コミュニケーションが得意な人とかオーガナイズするのが得意な人が出てきて、だんだんとグループをまとめるハブ的な存在になっていったんです。そこからマネージャーとか仕切りたがり屋みたいなのが生まれても不思議はないですよね。あとは、グループを始めた人が、”自分たちのデモはこうあるべき“っていう明確なビジョンを持っていて、そのビジョンから外れたことをさせないようにしたりとかですね。
もちろん、今はリアルタイムでコミュニケーションするための手段はそこらじゅうに転がっているので、作品を仕上げるのに厳格な組織構造は必要ないんです。それに、MediaWikiをサーバーにインストールしたからって、自分を偉大な人間だと勘違いする人もいないですからね、、少なくとも今のところは(笑) だからこそ、オールドスクールのグループが、Pouetみたいな公の場所で幼稚園レベルのケンカをしていると笑っちゃうんですよね。12歳の時に作ったルールが今でも通用すると思ってる40代の男たちが、怒りにまかせて長々とわめきちらしてるんです。その理由っていうのも、グループの誰かが2014年にリリースした作品が“80年代後半に存在した不可解なグループの戒律を破ったから”ってことだったりするんですよ。
でも大丈夫です。基本的にデモシーンの他の人たちは、グループ名がTRSIだろうがTだろうがRSIだろうが気にもしていませんから、、、っていうか、もういい加減にしてくれよ、、そんなに昔のルールにこだわるなら、家族に手紙でも書いて、そこに使い回しの切手を貼って楽しんだらどうかな?
(注:デモシーンの黄金期といわれる90年代初頭は、デモを入れたフロッピーなどを郵送で送り合う文化があった。あまりに配送先が多くお金がかかるので、古い切手を使いまわしていたという話がある。)
なるほど…、人間がいれば揉め事はあって当然なのかもしれませんね…。 でも、正直なところ、Farbrauschにリーダーや組織構造がないっていうのは意外でした。なんか、、ものすごい階級があるのかと勝手に想像していたんですが、、(笑) では、Farbrauschの制作プロセスについて教えていただけますか?
さっきも言ったように、Farbrauschは“作品を作る”という前提で動いているので、これと決まった制作プロセスがあるわけではないんです。5つデモがあれば方法も5通りあります。ただ、結果的に共通していることがあるとすれば、“誰かがアイデアを持ってきて、そのアイデアを気に入ったメンバーが参加する”ということですかね。
たとえば、“マルチコア物理を披露したい”っていうChaosのアイデアだったり、”ディスコデモがやりたい”と言い続けてきたFiver2のアイデアだったり…。ディスコデモはbloomエフェクトのおかげでようやく実現しましたけどね。あとは、EvokeでRygがいきなり”僕たちアートもできますっていうデモを作りたい”って言い出したところから、Ronnyが加わって「Cargo cult」が生まれたりしています。でも、アイデアが出てからの実際の制作プロセスっていうのは、それぞれで違いますね。
そうなんですね。では質問なんですが、Farbrauschの皆さんが滞在する「Elitehaus(エリートハウス)」とは何ですか?隠してもムダですよ、私は聞いたことがあるんです・・。ウワサではこの場所に来ると、すごい作品ができるとか…。
さっき制作プロセスは作品ごとに違うって言いましたけど、Elitehausの存在を考えると、プロセスがまったく異なるとは言い切れないですね。
Elitehausっていうのは、Elitegroupをやってる時に思いついたものなんです。あの時は“ここのボスは誰なのか”っていうのをシーンに見せ付けてやるような作品が必要で、それで1999年の12月にデンマークのバケーションハウスを借りました。ドイツの国境から1時間ぐらい、最寄りのスーパーまで10分ぐらいのところです。つまり、コンピュータとプールしかない場所に2週間閉じこもったんです。その甲斐あって、14日後には「Kasparov」はほぼ完成していましたし、数週間後のThe Party(デンマークで開催されていたデモパーティー)で仕上げることができました。あれは大成功でしたね。
それで、その時から現在にいたるまで、恒例行事みたいになってるんです。毎年はやってませんし、さすがに15年前のような激しいペースで作品を作ったりはしませんけど、「The Product」(動画)、「Poemtoahorse」(動画)、「The Popular Demo」(動画)、「Of Spirits Taken」(動画)、「Debris」、「Rove」(動画)、「Magellan」(動画)みたいなFarbrauschの“大作”と呼ばれるものは、ほとんどデンマークのバケーションハウスで制作されていますね。Farbrausch以外でも、ここに来た友達が作った作品もいろいろありますよ。たとえば、去年はMercuryのメンバーが参加して、この前Revisionでリリースした作品を作っていましたね。2005年にはPaniqが来て初日に2つの詩を見せてくれたので、その2つ目の詩がいいだろうということになって、「Die Ewigkeit Schmerzt」(動画)を作っていました。
“コンピュータとプールしかない場所に閉じこもる”っていうのが、ものすごく楽しそうに聞こえますね(笑) 他のグループと比べるとFarbrauschは作品に関わる人数が多い気がするんですが、これには何か理由があるのでしょうか?
Elitehausの雰囲気がそうさせるんでしょうね。別のプロジェクトに取り組んでいても、他の人のスクリーンは常に目に入ってきますし、そうすると自分がチームの一員になった気分になるんです。そこから何か役に立ちそうな提案をしたり、コードやグラフィックスの手伝いをするっていうのも、ごく自然な流れですね。たとえば「Rove」と「Magellan」の時は、自分のプロジェクトを持っていったにも関わらず、結局はコードの最適化を手伝っていましたね。ミリ秒単位でランタイムをかなり減らす必要があったんですが、Chaosはエフェクトの制作とデモ自体を完成させることで手一杯だったので、、。
なるほど。先ほどもちょっと出ましたが、Farbrauschの作品には、FR-からはじまる“製品コード”と呼ばれる番号がついていますよね。で、ジョークで作ったと思われる作品には、“FR-minus(マイナス)”の番号がついています。作品にマイナスをつけるかどうか、っていうのはグループで何か決まった基準があるのですか?
さっきもFarbrauschが最初に決めたルールは、”好きなことをやる”ってことだと説明しましたが、番号をつけるっていうルールも、わりと最初の頃に決まっていましたね。(必須じゃないですけどね。「Masagin」(動画)にはfr-の番号がついていないでしょう?) それと、見る人にヒントを与えるという意味で、本気の作品と遊びの作品を分けたほうがいいだろうということになっていたんです。でも、ルールと言ってもそのぐらいですね。実際、けっこうヒドイ作品でも正数になってるものもありますし、“fr-minus”になっていても、思い入れの強い作品はいくつかあります。基準はかなり曖昧なんです。
そうだったんですか!分厚いルールブックが存在するのかと思ってました(笑) そういえば、デモパーティーのライブ映像を見ると、スクリーンに“Farbrausch”の名前が出ただけで観客が大騒ぎしていますよね。ご自身でも実感されていると思いますが、そういう観客やファンからの大いなる期待っていうのは、kbさんにとって励みになるものですか?それともプレッシャーに感じていますか?
正直なところ、「The Product」と「The Popular Demo」の後は大変でした。今でも“Debrisみたいな大作じゃない”という理由で、2週間で作ったFarbrauschの作品をPouetで批判する人もいますよ。でも、そういう批評を受け入れて、今自分がやっていることを続けていくしかないんです。あるいは、その全く逆のことをやるとかね。実際、僕たちも「The Product」の1年後には、TP2001で「Farbomat」をリリースしています。
もちろん、僕だって他の人のデモを見ていて、”何であんなのをリリースできるんだ?見えてないのか?俺もグラフィックスは苦手だけど、でも、、いくら何でもあれはダメだろう…”って思うことは時々ありますよ。でもその1分後には、この自分の姿勢こそが、ここ3年間まともな作品を出してない理由なんだろうなって考えるんです。まあ、近年のデモパーティー会場のスクリーンで目にする“作品以外のすべて”、としておなじみのPartymeisterビームシステムは作りましたけどね(笑)
全く逆のことをする、っていうのは勇気がある行動ですね!(笑) でも、その後には必ずいろんな感想が出てきそうですが、、他の人からのコメントは気にしていますか?
もちろんです。世界と完全に切り離された状態で生活している人はいませんし、他の人からのフィードバックが重要じゃなかったら、わざわざデモパーティーで作品を出すなんてことしませんよ。パーティーでリリースするってことは、コンポの間は不安で小さくなってるってことですし、自分たちの作品が終わるとオーディエンスの反応に怯えるってことですから。こういうのを覚悟するか、まったく出さないかのどちらかですね。ただ、Farbrauschのメンバーはこういうのに慣れっこな人が多いので、安っぽい褒め言葉とかバカバカしい怒りのコメントなんかは簡単に無視できていて、信頼している人たちや鋭い指摘をする人の率直な意見だけを聞いていますね。
とりあえず、そんな考え方でやってます(笑)
そうでしたか、ありがとうございます(笑) ではグループから少し離れて、kbさんの個人的な制作プロセスなどお聞きしたいのですが、デモや音楽のインスピレーションはどんなところから得ていますか?
いろいろですね。頭の中で鳴っているメロディを表現したものだったり、レンダリング技術をいくつか試してみたいなと思って始めたものが、4kデモの「sunr4y」(video)みたいな流体プロセスになったりとか…。「Candytron」のサントラの時は、どんなジャンルの音楽にすればいいか数週間悩んでいたんですが、クラブで聞いた音楽にいきなりピンときて、“この方向性で行こう”って決めました。
でも、大抵の場合、僕にとっては曲を作るよりコードを書くほうが楽ですね。プログラミングはとても直線的な作業ですけど、作曲は良いアイデアが浮かぶかどうかにかかっていますから。浮かばなかった場合は、待つしかないんです。
*ちょっとセクシーなデモなので、学校や会社で見るときはご注意ください(笑)
どんなグループと作業するときでも、これだけは譲れない!というところや、自分なりのルールや目標を決めたりしていますか?デモや音楽を作るとき、特に気をつけていることがあれば教えてください。
気を付けていることと言えば、“作ったものを自分で気に入っていること”ぐらいですかね。曲だったら、5時間ループしてもイライラしないっていう基準をクリアする必要があって、制作に参加したデモだったら、自分が見ていて楽しいものにするべきだろうと思っています。もちろん、制作にかけた時間によって基準は変わりますけど、最終的には、完成品を見たり聞いたりした時に自分が気持ち良くないとダメですね。
作品を作る意味ってことで言うと、僕は自分のことをアーティストだとは思っていなくて、ただカッコ良いと思うものを作ったり、消費したりするのが好きな人間だと思っています。たしかに、過去にゴス文化に傾倒してたことが叙情的な”デモシーン・ポエム”を書くのに役立ってはいますけどね(笑)
そういえば、前に何かの記事でkbさんがゴス文化に出会った時のことを読みました。せっかくの機会なのでお聞きしますが、ゴス文化と、このギーク文化に何か共通点を感じますか?
これも、90年代にはもっと勢いがあったと言わざるを得ないものですね。ゴスとギークの最大の共通点は、幼少期に味わっていた“どこにも属していないような感覚”なんだと思います。だからこそ、“ふつうの人々”と呼ばれる世間に対してどこか見下しているようなところもありました。これがゴスとギークを結びつけるもので、だからこの2つは相性がわりと良かったりするんです。
ただ、今はギーク文化もゴス文化もメインストリーム化していて、ある意味カッコ良いものになってきちゃったので、残念ながらここ数年で下火になってきているんです。まぁ、まだ消えてはいないですけどね。
むむむ、なるほど…。なんだか論文のテーマになりそうな興味深い考察ですね!(笑) さて、では制作プロセスに話を戻しましょう。デモや音楽を作る時に、必ず夜中に作業するとか、ビールを飲むとか、作業するときの“こだわり”みたいなものはありますか?
時間とお茶は効果的ですね。でも、残念ながらフルタイムの仕事とプライベートの時間を引くと、デモシーンの活動に使える時間はそれほど多くないんです。だから、趣味でコーディングや作曲をしている時に陽の光を見ることはほとんどないですね。Elitehausは真冬のデンマークでやっているので昼の時間が短いですし、その半分は睡眠時間とかぶっているので…。だから、暗闇で作業してますね。それとお茶です。とにかくお茶をよく飲みます。作業中は必ずと言っていいほど、お茶の入ったコップやポットがそばにありますね。
あら、なんだか本格的! お気に入りの茶葉やおすすめがあれば教えてください!
いちばん好きなのは、ダージリンのファーストフラッシュですね。「TGFOP」(注:紅茶のグレードのこと)の前に文字があればあるほど良いです。香りの中にある繊細なデティールが好きなので、ジュンパナ茶園の紅茶がおすすめです(笑)
あとは緑茶(煎茶かジャスミン茶)も好きですし、白茶も時々飲みます(白雪龍–Bai Xue Long-茶がおすすめです)。キッチンにはフルーツティーとハーブティーがいろいろとストックしてあるので、遅い時間にはそういうのを飲みますね。
す、すごい、、、。キッチンがお茶屋さんの棚みたいになってそうですね(笑) では音楽はどうですか?作業中に音楽やピンクノイズを聞くとか、なにか自分なりの決まりごとはありますか?
コーディング中は、気が散らないように歌詞の少ないエレクトロニカを聞いていますね。右脳を動かしていられるだけの心地良いメロディーとハーモニーがあれば、左脳はアルゴリズムを生み出すことに集中できますから。知らない言葉の曲を聞くっていうのが効果的な場合もあります。あと1時間で何かを仕上げなきゃならないって時には、J-Popを聞くかもしれませんね(笑)
想像すると、ちょっと面白いですね(笑) では、残念ながら私には理解できない部分ですが、デモを制作している読者の方のためにお聞きします(笑) どんなプログラムを使ってデモや音楽を制作していますか?自作ツールを使っていますか?
Farbrauschはデモ制作にツール重視のアプローチをとることで知られているんですが、もちろん僕自身もそういうタイプです(笑) 実のところ、RygやChaosや僕みたいなコーダーはグラフィックスとかデザインがかなり苦手なので、“コーダーが片側からエフェクトを入れたら、それをアーティストが別の側で改良できるツールを作る”っていうのは、僕たちのスキルに合わせたものだったんですよ。「Werkkzeug」とか他のモジュラー型のデモ制作ツールも、基本的にはこういった感じで生まれました。
音楽についても同じです。64kイントロの曲を作ることになった時、“コーダーとしての自分”が、“ミュージシャンとしての自分”にとって使いやすいツールを作ろうと思いました。だからこそ、誰でもいろんな音楽ソフトウェアと組み合わせて使えるシンセサイザーになったんです。「The Product」の曲だったら、ソースファイルとかテキストエディタで作曲もできましたけど、コードで作った曲じゃなくて、リアルなサウンドにしたかったんですよね。そうすると、ワークフローもできるだけリアルなものにすることが最善策だろうと思いました。
“fr-08: .the.product” by Farbrausch (2000)
それ以外の必須ツールをざっと挙げると、コーディングにはほぼ何にでもVisual Studioだけを使っていますね。音楽だと、最近気に入っているソフトウェアはReaperで、それにプラグインをいろいろ入れています。あとは、普通のテキストエディタやファイルマネージャ、ちょっとしたコマンドラインツールを無数に組み合わせて自分が作業しやすい環境にしています。
それでは定番の質問にいきます。好きなデモ、心に残るデモ、影響を受けたデモ、、または人生を変えたデモ… kbさんにとって特別なデモを教えてください。
あれは1993年、実家のリビングでのことでしたね。友達から譲ってもらったAmiga500を何とか修理することに成功したので、大きなテレビとステレオにつないでみたんです。試しにと思って、箱から適当に取り出してAmigaのドライブに入れたのが(Spaceballsの)「State of the Art」(video)でした。それで見始めて5分後には分かったんです。僕は“ニュースクール”なんだな、って。
不思議なんですが、当時の僕にはAmigaの知識がほとんどなかったにも関わらず、このデモが技術的にそこまでスゴイものではないと何となく分かっていたんです。でも、何か新しくて刺激的なものを感じました。あの時を境に僕の中ではスクローラや黒いバックグラウンドにエフェクトをのせるっていうのは終わって、これからは何が出てくるんだろうって、新しいものを楽しみにするようになったんです。
20年以上前の作品を選んでますけど、それ以降の作品が良くないってことではないですよ(笑) 僕が”PCシーナー”の道を歩むきっかけになったのはFuture CrewとGravis Ultrasoundですし、デモシーンの新時代を切りひらいたのはDirectXとGeForceですからね。それに、ピクセルシェーダの登場で、デモシーンが新たな方向に向かい始めたんです。あまり進歩のない時もありましたけど、全体的に見ればワクワクすることばかりでしたね。
長い間、デモシーンの浮き沈みを体感してきた方のお言葉ですね…。Kbさんはデモシーナーの活動だけでなく、イースターの時期に開催されるドイツのデモパーティーのオーガナイザーをされていますよね。もう10年以上になると思うのですが、これほど長く続けられるのはなぜですか?
数年前のtUMパーティー(クリスマスと元旦の間にドイツで開催されるデモパーティー)に、「本当の家族と過ごすクリスマス」っていうキャッチコピーがついてたんですけど、まさにそんな感じですね。というか、もはや普通のイースターがどんなものだったかも思い出せないですし、そういうのをしたいかも分からないです。つまり、僕はまだデモシーンが大好きなんです。Revisionで担当してる仕事もすごく好きですし、会場に立ってコンポやイベントを見ているだけで、それまでの苦労が報われた気がします。
過去に「もうデモシーンは飽きたな!」と思ったことは一度もないのでしょうか?
そんなことあるんですかね?ここ数年、僕はあまり生産的な活動をしていなくて、“また作品を作らずにパーティーに来ちゃったな”と罪悪感を感じたりもしているんですが、それでも自分はデモシーンに属する人間だと強く感じています。正直なところ、デモシーンを辞める人っていうのは、もともとデモシーンっていう場所が合ってなかったんじゃないかと思いますね。ゲーム業界なんかには元シーナーやベテランと呼ばれる人たちがいますけど、こういう人たちは今でも新しいデモがリリースされると喜んで見ていますし、デモパーティーに参加したいと思っている人が多いんです。とくに「週末にRevisionに参加したことがきっかけで、数十年ぶりにカムバックを果たした」っていう人の話なんかを聞いたりするとね(笑)
それは素敵ですね! 今後はナイスミドルの作品にも期待しています(笑) 今後デモシーンはどんなふうになってほしいと思いますか?
まったく分かりませんけど、それがいいんです(笑) まぁ、正直なところ、オールドスクールプラットフォームへの執着を少しは捨てて、新しい表現方法を取り入れてほしいなとは思いますけどね。世の中には、“デモにわりと近いものを作っているけれど、デモシーンとはそれほど共通点がない”っていう人たちがたくさんいるんです。残念ながら、Revisionにこういう人たちを迎え入れようとすれば、多くのシーナーたちが“デモシーンの集まりじゃない!”といって気を悪くするでしょうね。実際、いろんなものが混ざったイベントだと、Assembly(フィンランドのイベント)を除いて、デモシーンの居場所があまりないんです。
でも、これはインタビューの中で語るには大きすぎる問題かな。今後に期待していましょう(笑)
そうですね!(笑) では、個人的に今後作ってみたいデモや音楽というのはありますか?
漠然としたアイデアはいろいろあるんですけど、まだしっかりとした形にはなっていないんです。チャンスがあれば仕上げられそうな音楽関連のプロジェクトはいくつかあるんですけどね。デモ作品だったら、今のレンダリング技術を使ったものが作ってみたいです。ハイダイナミックレンジとか物理ベースレンダリングとか、過去数年の間にものすごい進化を遂げているんですよね。そういう技術を、AAAタイトルと呼ばれるようなもの以外に使えたら楽しいだろうなと思っています。でも、さっきも言いましたけど、僕はビジュアル面はそれほど得意ではないですし、現世代のエンジンを作るにはすごく時間がかかるんですよ。エンジン自体を作るんじゃなくて、レンダリング用のちょっとしたコードを書くのでも、かなり時間が必要なんです。
まぁ、でもFarbrauschの他のメンバーに何かアイデアがあるでしょうから、それにいつでも貢献できればと思っています(笑)
それでは最後にデモシーナー、デモファンの方にメッセージをお願いします。
現在のシーナーにってことですか?
はい!それと、将来のデモシーナーや現在お休み中のデモシーナーの方にもお願いします!(笑)
デモを作りましょう。
まずは自分に合った開発環境を整えて、見込みのありそうなものをコーディングします。できたらスクリーンショットを撮って好きなデジタルアーティストに送り、手直しを依頼します。アーティストから戻ってきたら、それをコードで再現します。次にコード内の数値を変数にして、GNU Rocketに入れて遊びます。そして好みのスタイルのインディーズミュージシャンに連絡してビデオを送り、作品を1曲使わせてもらうか、新しい曲を作ってもらいます。曲を受け取ったらすべてを組み合わせてZipファイルに入れ、USBスティックとクラウドにコピーします。アルコール類を買って、近くで開催されているデモパーティーに参加します。作品を何人かに見せて微調節したら、エントリーしてアルコールの摂取を開始します。コンポが始まったら、ステージの前に座ります。
はい、これでデモの完成です。運が良ければ、製作途中でグループも結成できます。わりと簡単でしょう?
——————————————————————–
私のミーハーな質問にもすべて丁寧に回答してくださったkbさん、どうもありがとうございました! イメージとは違う、kbさんの新たな一面が見られた気がするのは私だけではないはず!
Kbさんのウェブサイトでは、ブログ記事やkbさんが手がけた作品のほかに、インタビューに出てきた自作のシンセサイザー「V2 synthesizer system」をダウンロードできます。また、Farbrauschのオフィシャルウェブサイト(ちょっとPouetと混同しそうな見た目ですが笑)では、Farbrauschの作品と、過去のElitehaus日記、「werkkzeug」を含むFarbrauschのデモツールのソースコード(!)がダウンロードできます(全部公開してるみたいです、トップの余裕ってやつなんでしょうか…)。
それから、Kbさんがゴス文化に傾倒した時のことなど、もっとkbさんのことを知りたい!という方は、こちらのZINEの記事がおすすめです!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
———————————————————————-
そもそも“デモ”ってなに?パソコンの話?と思った方は、まずはこちらのMoleman2のドキュメンタリーをチェック。(この映画の監督、シラードさんのインタビューはこちらでどうぞ。)
#1: 日本のデモシーナー、qさん(nonoil、gorakubuのコーダー)にインタビューは、こちら。
#2: デモシーナー、Gargajさん(Conspiracy、Ümlaüt Design)にインタビューは、こちら
#3: デモシーナー、Preacherさん(Brainstorm、Traction)にインタビューは、こちら。
#4: デモシーナー、Zavieさん(Ctrl-Alt-Test)にインタビューは、こちら。
#5: デモシーナー、Smashさん(Fairlight)にインタビューは、こちら。
#6: デモシーナー、Gloomさん(Excess、Dead Roman)にインタビューは、こちら。
#7: 日本のデモシーナー、kiokuさん(System K)にインタビューは、こちら。
#8: デモシーナー、kbさん(Farbrausch)にインタビューは、こちら。
#9: デモシーナー、iqさん(RGBA)にインタビューは、こちら。
#10: デモシーナー、Navisさん(Andromeda Software Development)にインタビューは、こちら。
#11: デモシーナー、Pixturさん(Still, LKCC)にインタビューは、こちら。
#12: デモシーナー、Crypticさん(Approximate)にインタビューは、こちら。
#13: 日本のデモシーナー、0x4015(よっしんさん)にインタビューは、こちら。
#14: デモシーナー、Flopine(Cookie Collective)にインタビューは、こちら。
#15:デモシーナー、nobyさん(Epoch、Prismbeings)にインタビューはこちら。
私がデモシーンに興味を持った理由、インタビューを始めた理由は、こちらの記事にまとめてあります。また、デモやデモシーンに関連する投稿はこちらからどうぞ。